※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
たとえば誰かと電話をしているとき。
姿の見えない相手に“もの”の良さを伝えるなら、どんなふうに話すだろう。

色、形、重さ、手触り、使い勝手、買ったお店、つくった人。
要素を並べるだけでは共感は生まれないし、長い話は飽きられる。実物を見せて「これ、いいでしょ?」と言うときとは違う難しさがある。
methodの仕事は、それと似たようなシチュエーションの連続かもしれません。
バイヤーの山田遊さんが代表を務めるmethodという会社は、お店づくりのディレクションやMD計画、イベント企画など、幅広いプロジェクトを手がけています。
今回は、プロジェクトマネージャーとしてここで一緒に働く人を募集します。ミュージアムショップから飲食店まで、さまざまな業態に携わるので、興味の範囲は広いほうがいいと思います。
渋谷駅から歩いて10分ほどのビルにmethodのオフィスはある。

なかには、気になるものがたくさん置いてある。
電話機の形をした電源タップ、インヴェーダーゲームの模様の畳。オブジェなのか、道具なのか。一体どこで買ってくるんだろう。
石の中に配線が隠されていたり、湯飲みが三角柱の形をしていたり。
壁に立てかけてある脚立も一見普通に見えるけど、何か意味がありそう。
「いや、あれは備品の脚立です。出しっ放しなだけですね(笑)」と、明るく答えてくれたのは、method代表の山田遊さん。
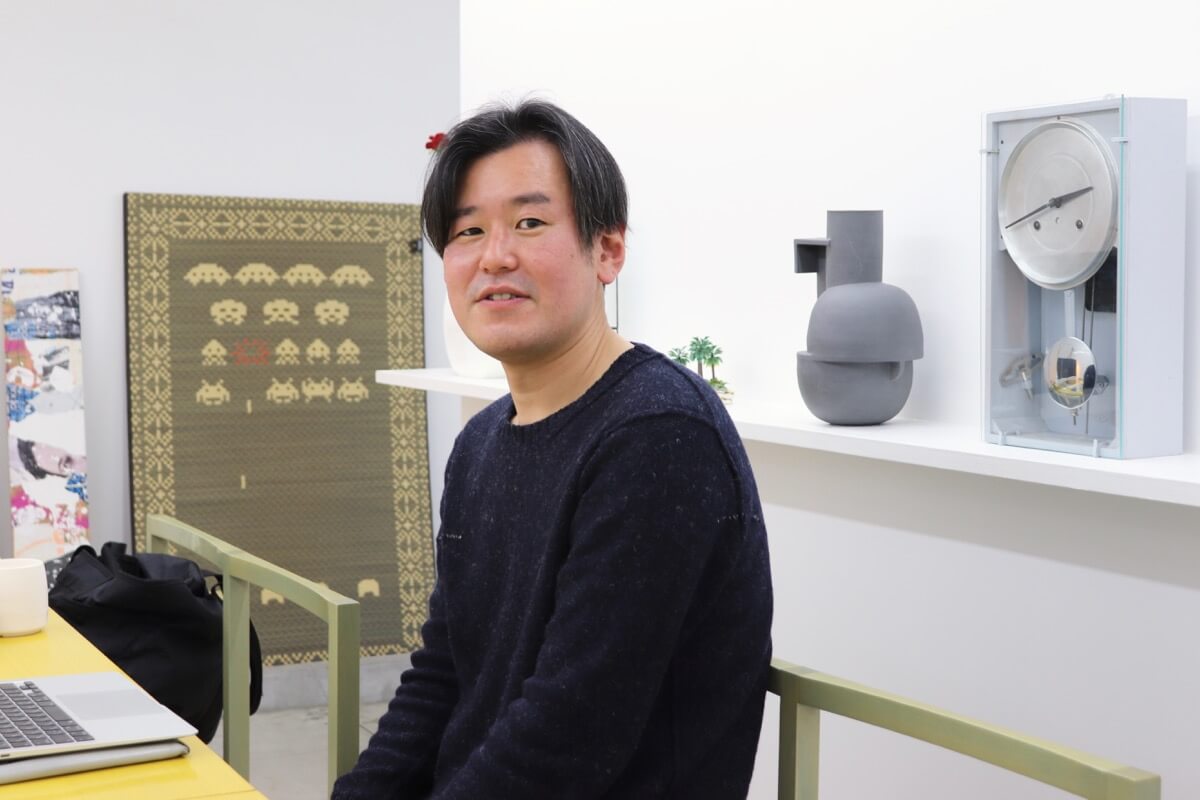
山田さんは自他ともに認める「ものオタク」。IDÉEのショップスタッフとして働いていた20代前半のころにバイヤーに抜擢され、その後フリーランスに。
国立新美術館のミュージアムショップや、中川政七商店など、物販の業態はもちろん、「燕三条工場の祭典」のようなイベント、飲食業態や、地方自治体とのプロジェクトなど、その仕事はバイヤーという肩書きでは捉えきれないほど幅広い。
「当初は雇われバイヤーとして、商品セレクトを頼まれることが多かったのですが、そもそも“お店がどうあるべきか?”が定まっていないと、ものが選べない。それでコンセプトづくりに介入するうちに、どんどん川上の仕事が増えていきました」
今では、新規プロジェクトの立ち上げや、課題を抱える店舗のテコ入れなど、何か困ったときに頼れる相談相手として声をかけられることが多い。

なかでも多く手がけてきたのが、お店づくり。
お店って以前は、特に用がなくても遊びに行ける場所だったけれど、「不要不急」という言葉が距離感を変えてしまった。
オンラインには、ものに関する「情報」があふれているのに、買い物の「体験」としては、どこか物足りない。いち消費者としては、そんなふうに感じることもあります。
「リアルなお店からECへ比重が大きくなるのは、コロナ禍にかかわらず既定事項で、『モノからコトへ』っていうのはずっと言われていた。僕自身も以前から『ストーリーを伝えよう』って意識してきました」
「一方でたしかに最近は少し、つくり手が雄弁になりすぎているかもしれない。今の時代に必要なのは、どちらかというとユーザーからのナラティブな言葉。だからこそ、自分の目で見て、手で触れて感じるお店での体験の価値を、あらためて見直す必要があるんじゃないかと思います」
ユーザーがものと出会う楽しさを伝えるためには、まず選ぶ側が体験してみることが重要。
現在、あるホテルで使う備品のセレクトをしている山田さん。カトラリーひとつ選ぶにも、数十種類を集めて比較するのだそう。

「重さや使い心地をたしかめながらひたすら使い倒す、千本ノックみたいな感じです。僕はものが好きだから、そういう細々した作業も苦にならないんですけど、やってみると結構大変だと思いますよ」
「仕事の幅が広がった今でも自分がバイヤーを名乗っているのは、そうやって“もの”を一つひとつたしかめる、初心を大事にしたいから。『ものにまつわる文化と関わり続ける会社』として、そこをおざなりにはしたくないんです」
一方で、変えるべきところは柔軟に。
日々変化していく社会のなかで、新しい発想を得るには、既存の“型”を外す必要がある。
「最近よく、飲食店で物販をやりたいっていう相談があるんです。レストランの片隅でお土産を売るっていうのは昔からあったけど、それをアップデートすれば、もっとおもしろいことができるんじゃないかっていう仮説はあります」
従来の“飲食店”という型を一旦脇に置き、食を楽しむ“場”としてどうあるべきかを考える。
要素を分解して、再構築すれば、社会が変化しても適応できる形が見えてくる。
それは、山田さんが自分のポジションを確立したプロセスにも似ている。

「僕の場合は、プロマネができて、仮説が立てられて、ものオタク、っていう3つの組み合わせで仕事をしていて。これから一緒に働くスタッフも、僕とは違う組み合わせでいいので、自分だけの特殊な一人称を見つけてほしいんです」
「たとえば、英語、文章、写真、パンが焼けるとか、喧嘩の仲裁がうまいとか。それぞれの個性を活かせば、同じプロジェクトマネージャーという役割でも、いろんな働き方が考えられる。特技を持ち寄って補いあえるのは、会社であることの価値だと思います」
プロマネと組み合わせられる、強み。
働きはじめて3年目の吉岡さんの場合は、デザインができること。

今年2月にオープンした日本橋三越本店のステーショナリーショップ「STAs」のプロジェクトでは、吉岡さんがロゴやビジュアルデザインを手がけた。
「前職はグラフィックデザイナーで、現在も個人で継続しています。以前は、ひとつの仕事に就くなら、それ以外のスキルや好奇心は一旦しまっておいたほうがいいのかなって思っていたのですが、methodではそれらを活かす場面があって」
「新しく入る人には、『自分が持つ特技を、全部抱きかかえた状態で大丈夫だよ』って伝えたいです」
とはいえ、プロジェクトマネジメントだけでも責任ある役割。まずは時間をかけて、一つずつ自分のものにしていってほしい。
プロジェクトはそれぞれ、山田さんと担当プロマネの組み合わせで進行する。吉岡さんが1年目に担当したのが、九州佐賀国際空港のお土産屋さんをリニューアルするプロジェクト。

「佐賀県内の産品を展開することは事前に決まっていたのですが、お店のコンセプト、名前、担当デザイナーや商品選びまで、考えることはたくさんあって。まずは地元の方とのヒアリングと、周辺環境のリサーチから取り掛かりました」
「空港は市の中心部から車で30分くらいの立地で、福岡や長崎の空港を使うほうが便利な場合もある。コロナ禍で飛行機の便数も不規則ななか、『これからのお土産屋さんの在り方』を考える事が重要でした」
今このような状況下で、ショップを立ち上げる意味ってなんだろう。
難しい状況だったからこそ、プロジェクトに関わる人たちが一緒に「そもそも」を考える機会になった。

「空港の屋上には有明海を見渡す展望デッキがあり、近くの公園には以前から家族連れが遊びに来ていました。そう考えると、ショップのお客さまは航空便の利用客だけじゃないかもしれない」
「来るたび新しい出会いや気づきが生まれて、地元の人にも愛されるショップを目指していこう、という方向性が見えてきました」
コンセプトが決まれば、次は商品のセレクト。
地元でヒアリングをしていて聞かれたのは、「佐賀には何もない」という声。
「本当に何もないのか、謙遜なのか、最初はわからなくて。ただ、調べていくと、さまざまな分野でのポテンシャルが高く、個人やチームで活動するプレイヤーも多いことがわかってきました」

老舗の銘菓や伝統工芸品はもちろん、小さな規模で活動するクリエイターにもスポットを当て、そろえた商品は約900点。
オープン1ヶ月前からは吉岡さんも佐賀に住み込んで、仕上げにかかった。
それは本来コロナ禍での出張頻度を減らす対策だったのだけど、滞在することで見えてきた価値もあったという。
「エアビーを借りて、空港やクライアントの会社に通う生活を送りました。一緒にご飯を食べたり冗談を言い合ったりするうちに、みんな同じ会社の同僚みたいな不思議な感覚になっていって」
methodのプロジェクトでは、普段から複数の企業や立場の異なる人とのチームで活動することが多い。
社内外の人とのコミュニケーションは、プロマネの仕事のなかでも大きなウェイトを占めるもの。
今回の募集要項を見ながら「この仕事内容、最初から全部に経験値の高い人は、そう多くはいないと思います(笑)」と話すのは、半年前に入社した金子さん。
前職は百貨店で、販売、催事、販促、仕入れなどを広く経験した金子さんでも、methodの業務はかなり幅広く感じるという。

入社後しばらくは、先輩スタッフのサポートを兼ねて現場に同行し、プロジェクトマネージャーとしての業務を覚えていく。
「たとえば六本木にある21_21 DESIGN SIGHTのショップでは、展覧会の企画会議から同席して、その内容に合わせたショップづくりをサポートさせてもらっています」
「前職の百貨店では自分たちの店や売場を基準に合うものを選んでいたのに対して、methodはほかの人の視点に立って考える。そこが難しくもあり、やりがいを感じるところでもあります」
第三者だからこそ、当事者の死角に気づくことができる。
オフィスに隣接したギャラリーの運営業務も、ものを見る目を鍛えるトレーニングになるという。

アパレルブランドの展示会や企画展などに使うこのギャラリー。会期中は、作家に代わってスタッフが作品の説明をすることも。
「考える余白を大切にしたいから、説明しすぎてはいけないし、情報不足でもいけない。鑑賞する位置一つで、作品の見え方も大きく変わる。まずは自分もお客さまと同じ目線に立って、ものと向き合ってみることが大切なのかもしれません」
それは山田さんの言う「千本ノック」に通じるやり方ですね。
「ひとつのものについてじっくり考えていくと、つくり手の姿も見えてくるし、ものを大切に扱おうという気持ちが芽生える。それが、たとえばプロジェクトでお借りしたサンプルを返却するときに丁寧に包んで返そうという意識にもつながると思うんです」
ものを見る目は、必ずしも天賦の才ではなく、日々の習慣を通じて養われていくもの。
繰り返し、見て考えるうちに、自分だけの物差しのようなものができていく。
仕事に昇華するまで、それを続けられるかどうかは、やっぱり「好き」という気持ちひとつだと思います。
(2022/3/3 取材 高橋佑香子)
※撮影時はマスクを外していただきました。





