※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
100人中、90人に受け入れられるものと、たった1人に届くもの。
そのどちらが価値あるものか、一概に示すことはできません。
前者を1万円で90人が買い、後者を90万円で1人が買えば、売り上げは同じ。大勢の手に渡るのも、大切な1人に届くのも、それぞれにしかない喜びがあります。
今回紹介するのは、コツコツ目の前の作業に向き合うような、ものづくりの仕事です。
長崎・波佐見の窯元、重山(じゅうざん)陶器で働く人を募集します。

求めているのは、絵付けを中心とした現場作業に携わりつつ、焼き物をデザインする人。
重山陶器では、今から50年ほど前にデザイン室を設け、オリジナルのものづくりに力を入れてきました。トレンドや需要の変化の波にさらされながらも、自社企画の器をつくり続けています。
かつて5人いたデザイン室のメンバーも、今は1名のみ。しかも、工場長や営業的な役割も兼任しているため、右腕となる人に来てもらいたいそうです。
どちらかといえば量産に近いけれど、地道な積み重ねのなかから、たしかに個性が滲み出る、焼き物の現場作業とデザイン。ハマる人がきっといる仕事だと思います。
長崎県で唯一海に面していない波佐見町。
まちの中心部には、窯元や商社、焼き物を扱うショップなどがずらりと並んでいる。
重山陶器があるのも、そんなまちの一角。陶器市などのイベントでよく使われるやきもの公園のすぐそばで、長崎空港からは50分ほどで到着する。
迎えてくれたのは、3代目の太田一彦さん。表情豊かに話してくれる気さくな方だ。

「うちは1930年創業です。祖父の娘婿に几帳面な人がいて、最初に窯入れしたときの記録が残っていたんですよ。もともとは中尾のほうで創業して、わたしも4歳まではそこで暮らしていました」
中尾は、ここから車で5分ほど行った先にある山間の地区。世界最大と言われる登り窯があり、江戸時代から日用食器を量産してきた。
人がひとり通るのがやっとの急な坂道をのぼった先に自宅兼工場があって、焼き物や資材を抱えて行き来していたという。
とにかく平地に下りたいという一心で、現在地へ移転してきたのが1963年のこと。

「当時にしては、結構進んだことをやっていたんです。このあたりで最初に社員食堂をつくったのもうち。それから、当時この隣にあった窯業試験場から指導を受けて、工場のレイアウトも整えて。生地が入ってきて出荷するまで、うまく流れる配置になっています」
1974年には、合理化モデル工場に選出。その後も設備のメンテナンスはしつつ、大幅にレイアウトを変えることなく、現在までものづくりを続けることができている。
そんななかで、重山陶器が大事にしてきたもののひとつがデザインだという。
「いつも親父が言うのが、デザインが一番むずかしいと。それで、デザイナーをとにかく入れたいってことで入れてですね。『芽生え』っていうシリーズを1974年につくりはじめて、これが大ヒットしたんです」

「一時は絵付7ラインすべてにこの柄が流れていましたから。今でもちょこちょこつくっては出していますよ」
バブル崩壊前の1985年には、工場を2階建てにして増産を考えるほど上昇気流に乗っていたそう。
ただ、景気の後退に伴って、拡張計画はストップ。カラーバリエーションや形状のトレンドも移り変わり、最盛期に従業員およそ100名のうち半数を占めていた絵付けのスタッフは、6人まで減った。
2030年で100周年を迎える重山陶器。次の100年につないでいくためにも、大事にしてきたデザインの担当とともに、技術を継承していける人を今回募集したいと考えている。
「デザインと並行して、現場の作業、とくに絵付けができる人を育てたいと思っています。絵付けだけでも『描き』『線引き』『イッチン』と、いろんな技術があって。軽作業だけど、専門性がいるんですよ。身につけるには、それなりに時間がかかります」
「ここからは、現場を見ながら話しましょうか」と一彦さん。作業場を案内してもらうことに。

入口は車が乗り入れられるようになっていて、軽トラックの荷台に積んだ生地がそのまま運び込まれてくる。
これを低温の窯で素焼きすると、白っぽい色からうすピンクに変色。
回転する羽根ぼうきのような機械やエアーガンを使って、ちりを落としていく。

続く絵付けのエリアでは、ラインごとにさまざまな技法で柄が描かれていく。
線を引く位置をレーザーポインターで示したり、焼き上げ時に消えるインクで“捨て判”と呼ばれるハンコを押して、その上からなぞったり。
量産のための工夫が随所に散りばめられている。
「あれも簡単そうに描いていますけど、むずかしいんですよ。線が途中で途切れないように、絵の具も特別な調合をしています」

釉薬をかけたら、本焼き。
窯に入れる際の配置にも気を配らなければならない。窯の何段目に入れるのか。台の中央か、外側か。
過去の焼き上がりの結果をもとに、すべての品番ごとにデータベース化して保存している。
そして、検品。ここにも重山陶器らしさが表れている。
「不良品をガサと言うんですが、その日出たガサは事務所前に置いておいて、誰でもチェックできるようにしているんです。たぶんよその会社はあまりやっていないことだと思う」
なぜやりはじめたんですか?
「前はうちもそうだったんだけど、ガサが出たときは、その作業の担当者に直接話しに行っていたんです。でも、本人は一生懸命やってるから、ある意味きついんですよね。どうしようって、ひとりで悩んでしまう」
「こうやってオープンにしていれば、声をかけ合えるし、何か気づいたら共有して、すぐに対応できる。昼休みは結構みんなここに集まって、『どうすれば直る?』とか、『これは仕方ないね』とかって話していますよ」
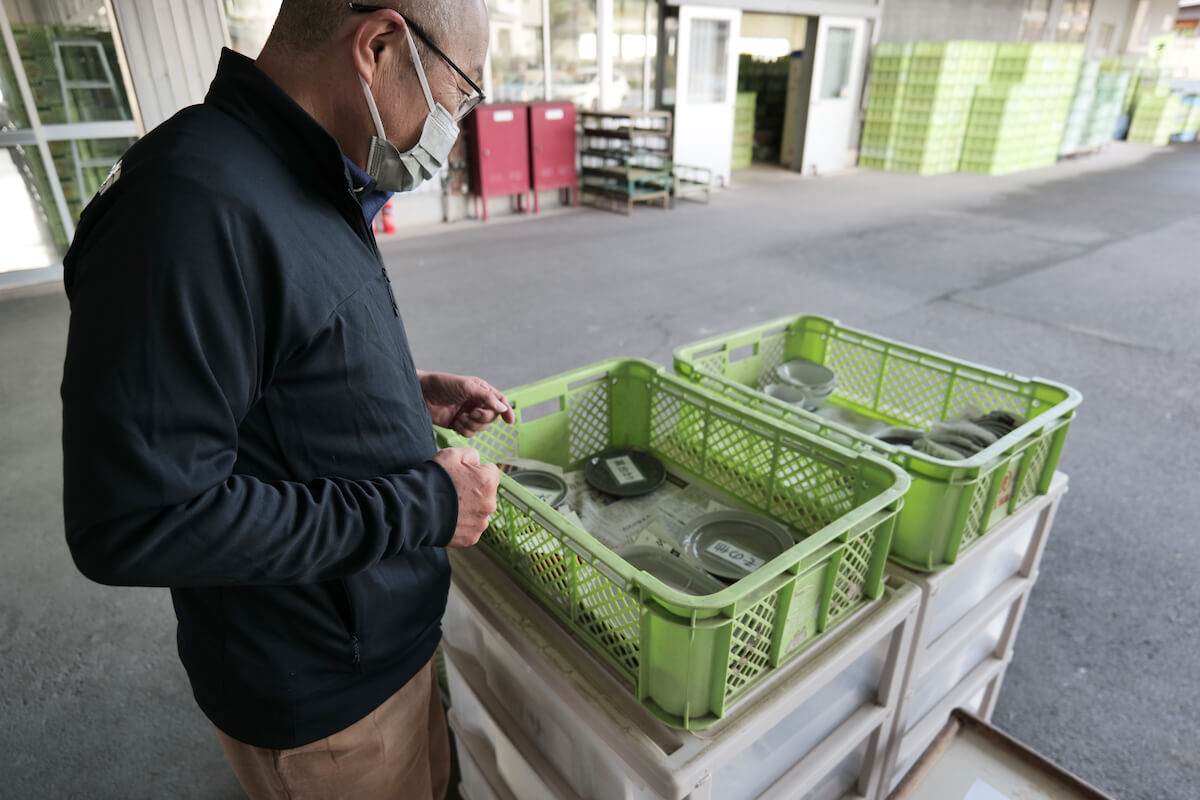
取引先の商社からは、「重山陶器の商品はほとんど検品しなくていい」というほどの評価を得ているそう。
この形をとることで、働く人の心理的な負荷を下げながら、品質を向上できている。シンプルながら、いい取り組みだなあ。
「デザインをするにしても、現場での経験が活きると思うんですよね」
そう話すのは、専務の太田幸子さん。

「たとえプロダクトデザインの経験があっても、曲線や変形ものも多い焼き物のデザインはむずかしいと思うんです。かかるコストや手間も理解したうえでいいものをつくる。そのためには、少なくとも1、2年はしっかりと現場に入ってもらう必要があると思います」
どうすれば、手間やコストを減らしながら、品質を上げられるか。
その発想は、個人作家にとっても必要なもの。
また、焼き物のつくり手からなる工業組合では、伝統工芸士による絵付けやロクロの勉強会も週に2回開かれている。長く勤め続けてもらえればベストだけど、将来の独立を見据えて経験を積みたいという人にとっても、いい環境だと思う。

幸子さんは、どんな人が合うと思いますか。
「誰かに言われなくても、自分で目標を立ててコツコツ取り組める人。向き不向きもあると思います。細い線は得意だけど、太い線は苦手とか。器の真ん中にハンコを押すのも、ある意味才能なんですよ。わたしはダメだった人(笑)。コツコツ力が大事なんじゃないかな」
最後に話を聞いたのは、デザイン担当と工場長を兼任している太田賢治さん。今回は賢治さんの右腕となる人を募集したい。
「デザイナーはあまり前に出ないほうがいいと思う」とのことで、写真はNG。そのぶん、これまでデザインしてきたものを手に取りながら、想いを聞かせてくれた。

「デザインするときに意識しているのは、重すぎない、持ちやすいとか、使い勝手のよさですね。あとは生産性、コストや手間と価格のバランス。賞とかにはまったく興味がないですし、自己満足じゃだめなので。やっぱり売れることが一番の喜びですね」
製造過程のさまざまな制約も理解しているからこそ、総合的なバランスを考えたものづくりができている。
そのなかに遊び心も垣間見える。たとえば、コーヒーのペーパーフィルターの形をしたプレートや、パカッと開くマカロンのような蓋物など。
メインターゲットである若年層の女性の気持ちやトレンドを汲みながら、デザインを考えていくという。

今回入る人の仕事は、まずは絵付けや釉薬掛けをはじめとした現場作業から。
そこで知見や技術を磨いたうえで、デザインにも幅を広げていってほしい。ゆくゆくは賢治さんと同じように、生産管理や商社とのやりとりなどもトータルでできる人を育てていきたい。
「まずは素直に聞いてくれる人がいいですね。こちらから指示することもあるし、ダメ出しもするので。自分も若いときはそうでしたけど、自分でつくったものは思い入れがあるから、すぐに受け入れられないんですよね。でもやっぱり、謙虚に受け止めることは大事だなって」
「デザインに関して、こうでなくては、というこだわりはないです。わたしと似たようなものをつくっても意味がないし、むしろないものをつくって結果が出たら、それが会社のためにもなるので。別物をつくれる人がいいですね」
窯業技術センターにある3Dプリンターを使って、新しい形状をつくる人がいてもいいかもしれない。重山陶器の生産体制をよく理解できてさえいれば、新しい技術も取り入れていってほしいと賢治さんは話す。
そんな話を隣で聞いていた、代表の一彦さん。
「産地のネームバリューとして、波佐見はまだまだ知られていないんですよ。だから伸び代があるわけです、逆に言ったらね。これからも焼き物をつくり続けたいし、波佐見という産地をもっと世に出していかないといけないときだと思っています」
一彦さんは波佐見焼工業組合の理事長も務めていて、組合としてもさまざまな取り組みを進めている。
たとえば、摩耗した石膏型の再活用。これまでは廃棄されてきたものを農業用の肥料としてリサイクルし、その肥料で育てた米を「八三三米」として、焼き物とセットで販売している。
また、米粉に加工してクッキーやカステラをつくり、販売していく流れもある。地場の企業や農家さん、観光協会や行政など、地域一体となって産業と環境を守る活動に発展しつつあるそうだ。

コツコツと積み重ねる日々のなかにこそ、見えてくるアイデアやデザインがある。
迷いそうになったら手を動かして、閃いたら誰かに話してみる。
そんな小気味よいリズムを刻めるようになれば、きっとこのまちで、楽しく働いて生きていけると思います。
(2022/11/21 取材 中川晃輔)
※撮影時はマスクを外していただきました。







