※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。
教科書を使った学習だけでなく、自分の暮らす地域の魅力を見つけることから学びを得る。人口減少など、地域の課題を逆手にとって、将来必要となる力を培っていく。
そんな地域をフィールドにした教育が、全国で少しずつ広がりを見せています。
 広島県大崎上島町にある大崎海星高校。
広島県大崎上島町にある大崎海星高校。地域の特色を活かした「カリキュラムづくり」、生徒たちの学力向上と進路をサポートする「公営塾の運営」、地域外からの生徒を受け入れる「教育寮の設置」の3つを柱に、魅力ある学校づくりを進める「高校魅力化プロジェクト」に取り組んできました。
このプロジェクトでは、学校の先生や地域で働く大人たちなど、立場の異なる人たちが一丸となり、町の子どもたちの教育を通じて島の未来に向き合っています。
大崎上島町を訪ねて感じたのは、全員野球のような一体感でした。
今回は、子どもたちの学習サポートを行う公営塾のスタッフと、寮生活を支えるハウスマスターを募集します。
広島空港から、乗り合いの大型タクシーで竹原港へ。
大崎上島町まではフェリーで30分ほど。船が動き出すと、さっそく穏やかな瀬戸内海の景色が迎えてくれる。
 温暖な気候に恵まれた大崎上島では、みかんなど柑橘類の栽培が盛ん。水産業や造船業も、主要な産業になっている。
温暖な気候に恵まれた大崎上島では、みかんなど柑橘類の栽培が盛ん。水産業や造船業も、主要な産業になっている。古くから海運の拠点として栄えた地域で、木造の和船「櫂伝馬(かいでんま)」に乗って速さを競う行事など、伝統文化や祭りも受け継がれている。
 この島にある大崎海星高校は、そんな島特有の自然や文化、歴史を教材に、「大崎上島学」という独自の授業を行っている。
この島にある大崎海星高校は、そんな島特有の自然や文化、歴史を教材に、「大崎上島学」という独自の授業を行っている。「潮目学」「羅針盤学」「航界学」の3つからなる大崎上島学。
たとえば「潮目学」では、生徒が町の中でフィールドワークをしながら、時代の流れを読み解く力を身につけていく。
今年は、塩田跡地を活用して牡蠣の養殖業を営む方など地域の事業者さんへインタビューをして、町の産業の課題を知り、先進事例を調べながら、自分たちで考えた解決策をプレゼンテーションとしてまとめた。
 ほかにも、2017年からはじまった「みりょくゆうびん局」では、生徒が中心となって、島内外に向けて自分たちの学校や島の魅力を発信する活動を行っている。
ほかにも、2017年からはじまった「みりょくゆうびん局」では、生徒が中心となって、島内外に向けて自分たちの学校や島の魅力を発信する活動を行っている。学校説明会などのプレゼンテーションでは、原稿を暗記して読み上げるだけではなく、聞いてくれる人の顔を見たり、抑揚のつけ方を意識したり。
生徒自らの工夫で、活動が進んでいくことも増えてきた。
堂々とした生徒さんたちの姿を見て、「想像以上に生徒たちの成長のスピードが速い」とうれしそうに話すのは、中原校長先生。
印象に残っているという出来事を話してくれた。
 「うちの生徒たちは、東京や大阪で行われる合同学校説明会にも参加しとって。2日間、午前午後とプログラムがあるんじゃけど、午前の部が終わったらすぐ自分たちで集まって、発表の振り返りをするんよ」
「うちの生徒たちは、東京や大阪で行われる合同学校説明会にも参加しとって。2日間、午前午後とプログラムがあるんじゃけど、午前の部が終わったらすぐ自分たちで集まって、発表の振り返りをするんよ」聞き手の反応を踏まえて、重点の置きどころやキーワードを見直し、ブラッシュアップさせて午後の部に臨む。
終了後にふたたびミーティング。翌日も改善点を反映して発表し、最初と最後ではまったくちがうものになった。
「問題意識やより良いものにしようという意思を持っとる証拠。課題を発見し、改善していく力を身につけていれば、将来どこに行っても活躍できると思うね」
 そんな取り組みが注目を集め、大崎海星高校への入学希望者は少しずつ増加。大学と連携した活動・交流の機会も増えてきている。
そんな取り組みが注目を集め、大崎海星高校への入学希望者は少しずつ増加。大学と連携した活動・交流の機会も増えてきている。「失敗してもいいから、学校の外に出てさまざまな体験をさせる。それが、生徒たちの視野を広げることにつながる。我々も公営塾のスタッフも、最大の役目は生徒たちの心に火をつけること。それができれば、あとは自分でどんどん学んでいくよ」
積極的かつ懐の深い先生たちがいることで、公営塾のスタッフものびのびと役割の幅を広げているよう。
2018年4月から町の公営塾「神峰学舎」のスタッフとして、魅力化プロジェクトに加わった笠井さんはこう話す。
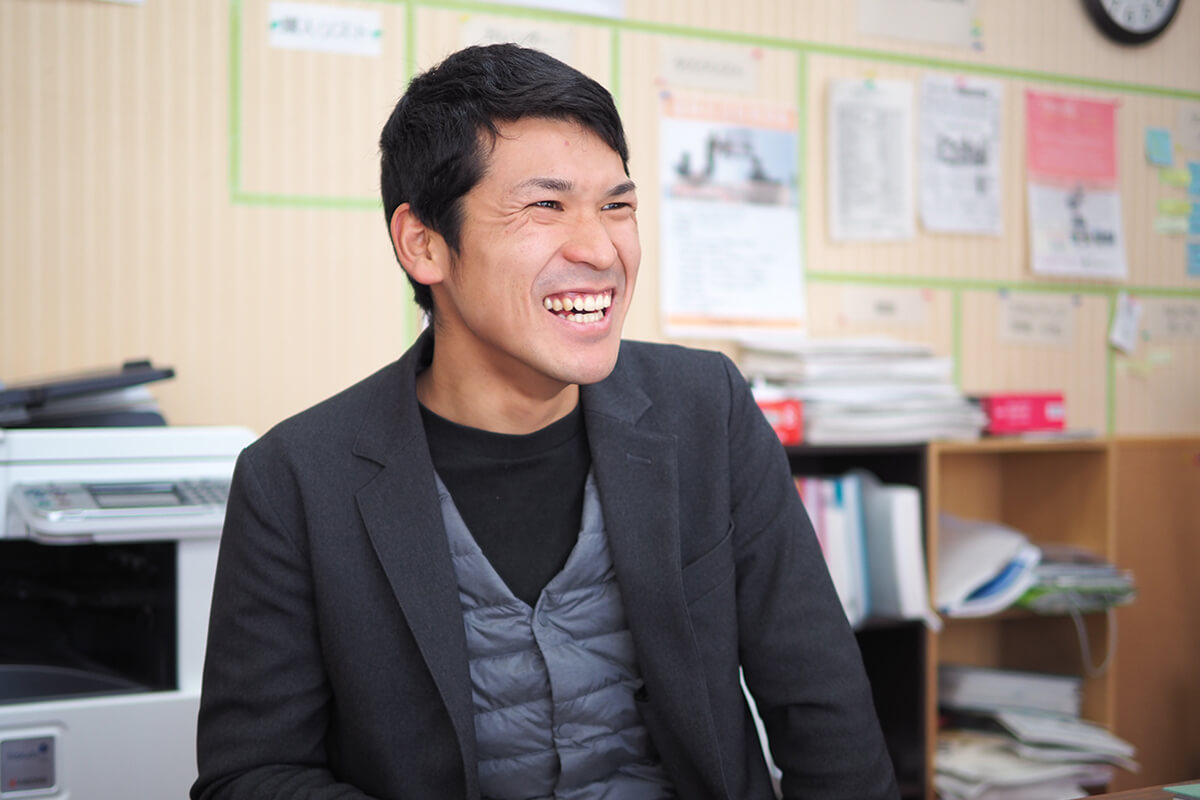 「この島では、いろんな人を巻き込んで、全員野球で教育に向き合っています。地元出身の魅力化コーディネーターが仕掛け人となって、学校の先生や地域の人、島外の人をつなぎながら、学びの場をひらいているんです」
「この島では、いろんな人を巻き込んで、全員野球で教育に向き合っています。地元出身の魅力化コーディネーターが仕掛け人となって、学校の先生や地域の人、島外の人をつなぎながら、学びの場をひらいているんです」笠井さんは大学在学中から、まちづくりと教育を掛け合わせた仕事をしたいと考えてきた。
大学4年生のときには、広島県内の別の地域で寺子屋のような私塾を立ち上げ、現在も運営を続けながら神峰学舎で働いている。
そんな笠井さんが公営塾で担当しているのが「夢⭐︎ラボ」。生徒たちが今の自分や将来の目標について探究していくキャリア学習の時間だ。
「僕がここでやりたいのは、キャリア教育を通じて公営塾と学校をつなげること。今は、大崎上島学にも少しずつ関わらせてもらっています。相乗効果を生みながら、生徒たちの主体性を伸ばしていきたいです」
神峰学舎の役割は、生徒一人ひとりが望む道に進んでいけるようサポートすること。
スタッフも一人ひとり、自分にできることを主体的に考えている。
2018年の4月から働く平岡さんは、自身が提案してはじまった企画について教えてくれた。
 「生徒と塾スタッフのやりたいことを自由に書いていい掲示板をつくりました。賛同した生徒とスタッフ一人ずつの名前が書き込まれると成立して、実行に向けて進めていくというものです」
「生徒と塾スタッフのやりたいことを自由に書いていい掲示板をつくりました。賛同した生徒とスタッフ一人ずつの名前が書き込まれると成立して、実行に向けて進めていくというものです」普段は、主に英語の教科指導を担当している平岡さん。
掲示板に「洋書を読みたい」と提案してみたところ、2年生のある生徒から反応があった。
「その子は、学校での勉強進度に遅れを感じていました。ただ、理解力は優れていて、大学進学も視野に入れつつ、自分に合った勉強方法を探していたんです」
洋書を一文一文読みながら、その子のペースで理解していけたら、受験に必要な英語力の強化にもつながる。
平岡さんはさっそく、その子にどんな本を読みたいか尋ねてみた。
「彼女があげたのは、エドガー・アラン・ポーという詩人の本。近代推理小説の開祖と称されていて、その子が好きな江戸川乱歩の名前の由来にもなった人物なんだと教えてくれて。今まで知らなかった一面にも気づけました」
きっと、平岡さんと一緒にやることで、生徒さんは一歩踏み出せたんだと思う。
生徒と共有する時間を大事にするために、スタッフはそれぞれのやり方で工夫している。
神峰学舎のスタッフとなって2年目、主に数学を担当しているのが牧内さん。今は学校での授業にも参加するようにしているとか。
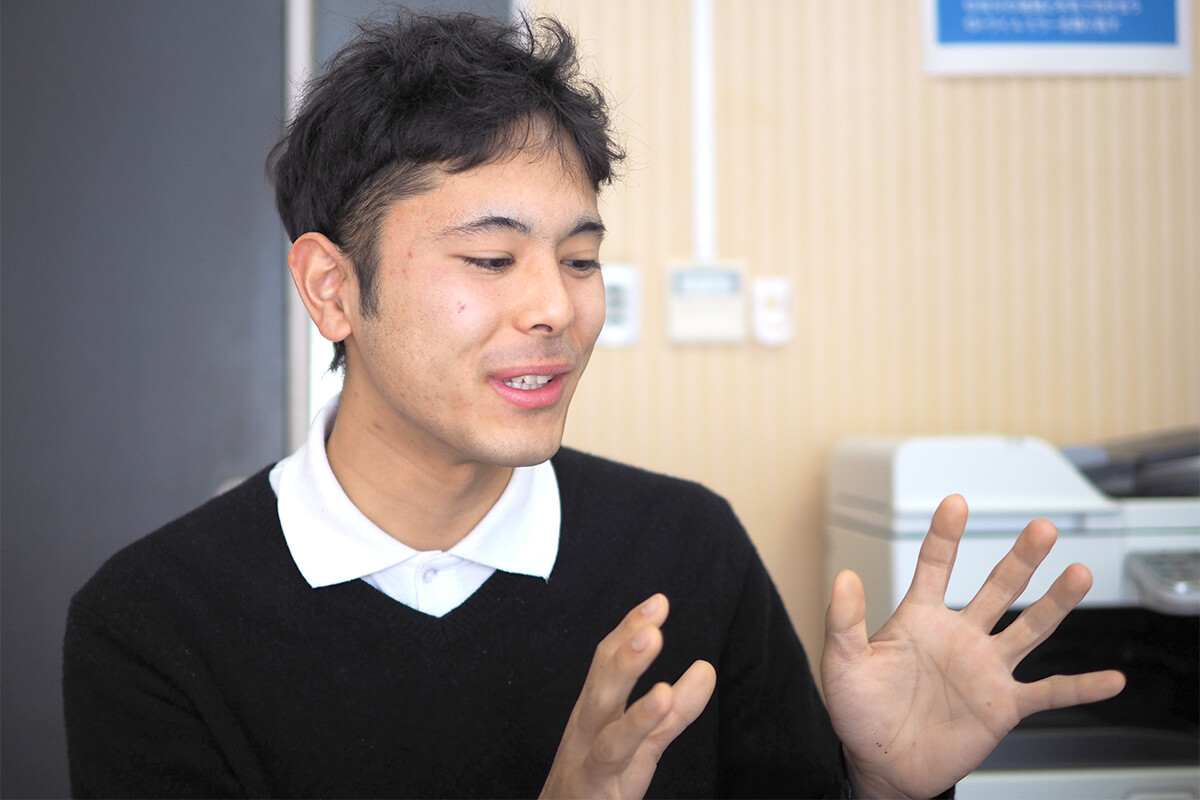 「授業に参加することで教え方の引き出しも増えるし、生徒との共通言語を持てるかなと思って」
「授業に参加することで教え方の引き出しも増えるし、生徒との共通言語を持てるかなと思って」共通言語。
「はい。僕も同じ授業を受けていることを知っていたら、わからないことを一から質問しなくても、『あれってどういう意味だったん?』『あとで行くから塾で教えて』とか、授業の続きみたいに話しやすくなると思うんです。僕も授業を踏まえて、教えたりできるし」
理解状況やモチベーションが生徒によって違っても、それぞれに応じた柔軟な学習スタイルをつくっていける良さが、公営塾にはある。
「裁量が大きい分、何が生徒にとっていいのかを常に考え、それを信じて生徒に接していかないといけません。大切なのは、生徒中心に考えていくこと。悩みながらも、前を向いてやっています」
同じく生徒に向き合う仕事でも、少し立場が異なるのが、生徒たちが生活する教育寮のハウスマスター。
2017年度まで公営塾のスタッフを務め、2018年度からハウスマスターとなった伊達さんに話を聞いた。
 「賛同し合うのではなく、理解を深めること。タイプの異なる人同士がそれぞれを認め合い、安心して暮らせる。そんな場をつくることに関心があって、ハウスマスターになったんです」
「賛同し合うのではなく、理解を深めること。タイプの異なる人同士がそれぞれを認め合い、安心して暮らせる。そんな場をつくることに関心があって、ハウスマスターになったんです」ハウスマスターの主な仕事は、親元を離れて暮らす生徒たちへの生活指導や精神面でのサポート。
保護者や学校、島の人たちと連携しながら、日々の寮の運営だけでなく季節ごとのイベントを企画することもある。
仕事の時間は朝6時半から9時までと、17時から22時半まで。
ある意味、生徒たちと一緒に暮らすことが仕事、とも言える。
午前中は、朝起きてこない生徒を起こしに行ったり、朝ごはんを食べたかどうかチェックしたり。欠席遅刻があれば学校に連絡。
夕方には、学校から帰ってくる寮生を「おかえり」と迎え、夕食までその日の出来事を聞いたりしながら過ごす。晩ご飯のあとは、気にかかる生徒とゆっくり話す時間をつくったり、合間を縫って資料作成などの事務作業をしたり。
 多感な時期の子どもたちの、共同生活。
多感な時期の子どもたちの、共同生活。伊達さんは、相手の気持ちや些細な変化にも気づけるように心がけている。
「夏のイベントで肝試しをしたとき、終わって帰ってきたらある女子の寮生がいつもと違う様子だったんです。だから、『ごめん何かあったよね。言えるタイミングになったら、機嫌を損ねている理由を教えてほしい』と伝えました」
強引に理由を聞き出したり、勝手な憶測で決めつけたりせず、気持ちに寄り添う。
しばらく待っていると、女の子は自分から理由を話してくれた。
「共有スペースに置いてあった彼女のぬいぐるみを、勝手に肝試しのおばけとして使ってしまったことが嫌だったみたいで」
伊達さんが大人として上からではなく対等に向き合うことで、正直に気持ちを伝えることができた。お互いに、もやもやした気持ちが解消されて女の子とも仲直りができた。
話しやすい身近な存在であるだけでなく、ときには抑止力になることも大事だと伊達さんは話す。
「みんなが気持ち良く暮らすためには、秩序を保つことが必要だということをちゃんとわかってほしい。だから今はルールを明確にしています」
それでもそれぞれの生活習慣などは簡単に直らず、朝起きられないなど、同じことを繰り返す寮生もいて、厳しい口調で接することもあるという。
我慢強さは必要になりそうですね。
「絶対にいると思います。自分の価値観を押し付けず、相手のことをちゃんと理解しようとする人と働きたいです。あとは、学校と寮とを行き来する生徒たちの毎日が少しでも晴れやかになるように、楽しみをつくれる人は必要だなと思っています」
正解のないなかで試行錯誤を続ける、公営塾のスタッフ、ハウスマスターたち。
そんな彼らの姿をたくましいと評価する地域の方の声も聞きました。
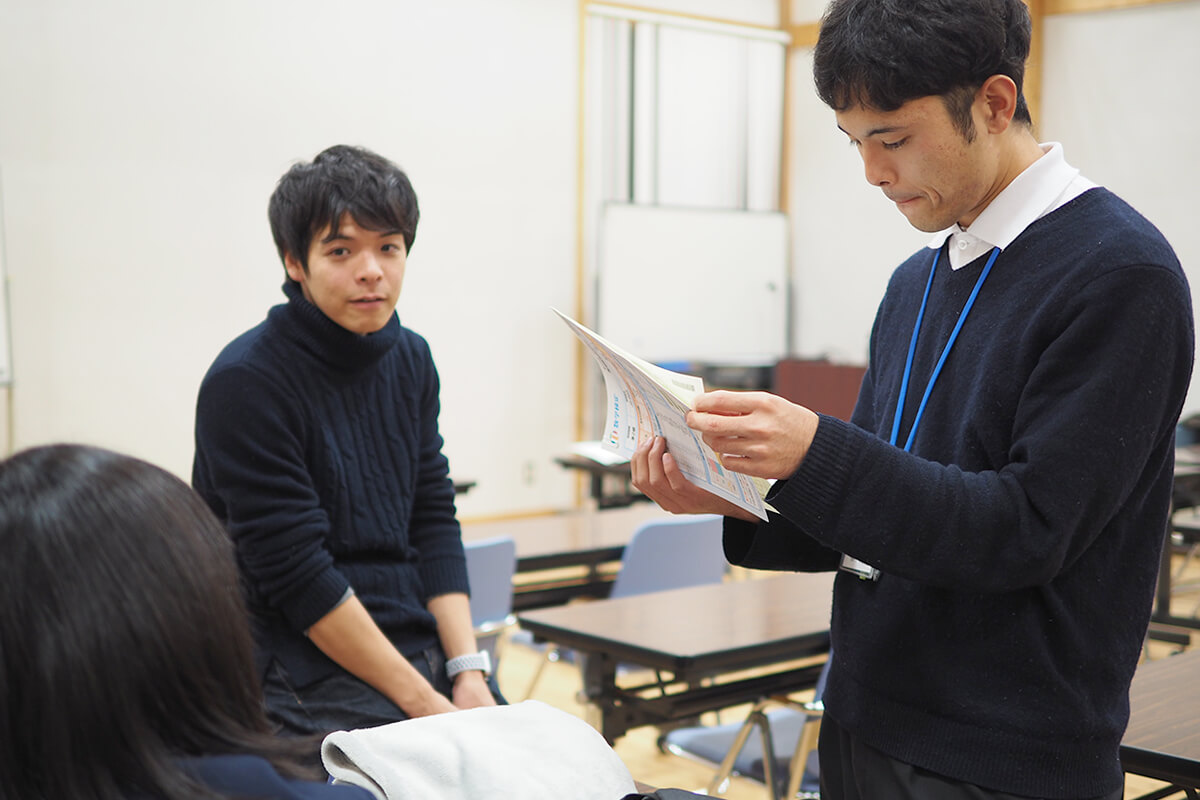 2/2(土)には、ハウスマスターの伊達さんもゲストとして参加するしごとバーを開催します。
2/2(土)には、ハウスマスターの伊達さんもゲストとして参加するしごとバーを開催します。迷っている方も、ぜひ等身大のまま、話をしてみてください。
(2019/12/17 取材 後藤響子)







